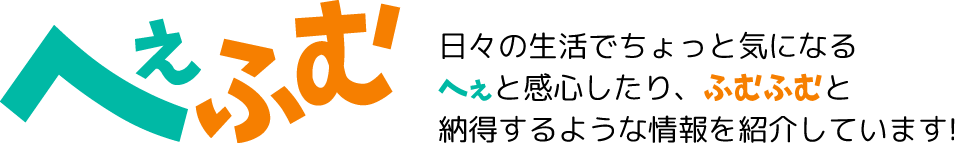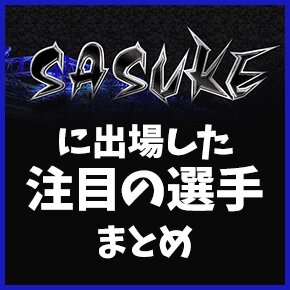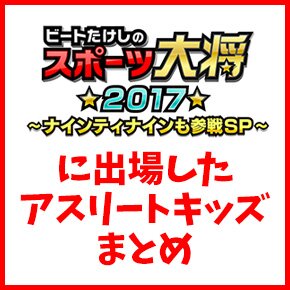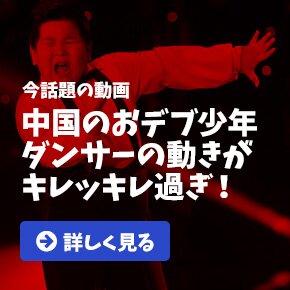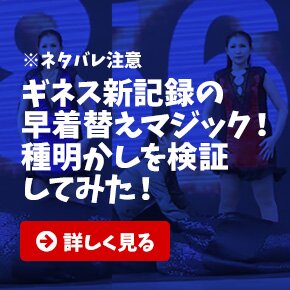有田陶器市は年々多くの来場者が訪れる人気の陶器市となっていますが、来場者が多いと問題になるのが、駐車場や周辺道路の渋滞。そこで今回は、有田陶器市の開催期間やみどころと合わせて、駐車場や渋滞を回避するアクセス方法などについてまとめてみました。
Contents
有田陶器市2017の開催日時は?
今年の有田陶器市は第114回を迎えるそうですが、2017年の開催期間は4月29日(土)~5月5日(金)となっています。
お店が開く時間帯はお店によって異なりますが、早いところでは朝6時ぐらいから開いており、多くのお店が夕方7時ぐらいまでやっているそうです。
有田陶器市の開催期間中は、毎日朝から晩まで有田焼の掘り出しもを探すことができます。
有田陶器市の開催期間中は掘り出し物探しで忙しいですが、有田陶器市で買った戦利品は、持ち帰ってゆっくり楽しみたいですね。
有田陶器市開催期間中の渋滞を避ける方法は?
有田陶器市は毎年多くの来場者があるので、有田陶器市の開催期間中は会場周辺道路が渋滞になることは間違いないですが、渋滞を避けるにはどうすればいいのでしょうか?
まず考えられるのが、渋滞する時間帯を避けること。
有田陶器市は朝6時ごろから開くお店もありますが、10時前後に着く来場者が多いようです。
また、お店は夜の7時くらいまで開いていますが、多くの人が17時くらいには会場を出るので、17時前が渋滞になるようです。
これを踏まえると、有田陶器市の会場周辺道路が渋滞するピークは、例年朝が9:00~11:00、夕方が15:00~17:00くらいになるようです。
この時間を避けることで渋滞もある程度は避けることができますが、おすすめなのは、ちょっと早起きして朝の6時ごろ会場に着くように行くこと。
早起きは苦手という人もいるかもしれませんが、朝早くから開けているお店もあるので、渋滞も回避できるし、会場もまだ人も少ないのでゆっくりとお店をまわることができるでしょう。
有田陶器市開催期間中の駐車場は?
有田陶器市の期間中、町内の各箇所に臨時の公営駐車場が設けられます(料金500円)。
しかし近くの駐車場は朝8時ぐらいには満車になります。
さきほどの渋滞のところでも言いましたが、駐車場のことを考えてもできるだけ早い時間に現地に着くようにしたほうがいいでしょう。
もし、朝早起きができないという場合は、会場近くまで行かずに大型の駐車場に停めて、無料のシャトルバスを利用してメインストリートへ行くことで渋滞を回避する方法もあります。
おすすめの駐車場
| 駐車場名 | 駐車台数 | 料金 | 会場へのアクセス |
|---|---|---|---|
| 有田ボーセリンパーク | 1000台 | 無料 | メインストリートへのシャトルバスが出る |
| 有田陶磁の里プラザ | 800台 | 無料 | メインストリートへのシャトルバスが出る(年中無休のショッピングモールで、老舗22店が入っており、雨の日でもここで楽しめる) |
| 桑古場駐車場 | 100台 | 料金500円 | 波佐見有田インターに近い |
| 有田小学校(平日14時から) | 300台 | 料金500円 | メイン会場から近い |
| 有田中学校(平日不可) | 650台 | 料金500円 | |
| ひらき球場 | 300台 | 料金500円 | 国道35号線に面していてメインストリートまで徒歩10分と近い |
近隣の県からは旅行会社による日帰りバスツアーなども企画されているのでそういったツアーを利用すれば交通機関や駐車場の心配はしなくてすむかもしれません。
有田陶器市会場へのアクセス情報
車の場合
車で出かける場合、西九州自動車道波佐見有田ICからは大変混雑しますので、あらかじめルートや駐車場をチェックしておくことが大切です。
車の場合は西九州自動車道波佐見有田ICより約5分です。
電車の場合
JR有田駅下車
期間中は博多からは快速有田陶器市号という臨時列車も出ます。
また博多発特急みどり号・ハウステンボス号が上有田駅に臨時停車します。
有田駅と九州陶磁文化館、ボーセリングパークの区間で無料シャトルバス(12:00~17:00)が運行されメイン会場まで行くことができます。
有田陶器市の会場は?
JR有田駅から上有田駅までの約4kmを中心にして町内一円に約600店の有田焼のお店が出ます。
まずは無料のガイドマップを手に入れて、上手に見て回りましょう。
ガイドマップはネットでも事前に手に入るので実際に行く前にシュミレーションをしておくのもよいかもしれません。

出典:http://www.wazangama.co.jp/
有田陶器市の見どころは?
やはり一番の楽しみは高級陶磁器として知られている有田焼をお買い得価格で購入できるということでしょう。
多少傷があっても家で使うには申し分のないものや規格外のもの、半端もの、有名ブランドのアウトレット品などの掘り出し物を見つけるという楽しみ、そして、それらの品を割引価格や中には半額で購入できるというお得さが有田陶器市の魅力といえます。
また、そうした楽しみの他にもさまざまなイベントが用意されています。
今年は、食器の使い方や食卓の演出の仕方などを提案する街角テーブルコーディネート展、高校生が考案した有田焼の文様の紙コップを使用したトンバイ塀の通りのカフェも登場します。
また有田焼カレーなどの有田グルメだけでなく県内外のご当地グルメが味わえるご当地グルメフェアも開催されますよ。
さらに100人が参加する仮装パレード(5月5日 11:00 スタート)では、有田焼の生みの親といわれる李参平など有田の歴史を彩った人物が登場します。
有田陶器市の前身となる品評会がおこなわれたという桂雲寺では、お茶会や有田伝統の皿かぶり競争が行われます。
皿かぶり競争はお皿を頭の上にのせて境内20mぐらいを競争するもので、1位になると商品券がもらえますよ。
ちなみにこの皿かぶり競争は有田では小学校の運動会の競技にもなっているとか。
毎年恒例の朝粥や、チャリティ福袋の販売、写真コンテスト、スタンプラリーなどもあります。
さらに有田国際陶磁展や伊万里・有田焼伝統工芸士展、陶祖祭などが協賛行事として行われ、陶器市を盛り上げています。
有田陶器市の歴史
有田はもともと弘法大師が開山された黒髪山にやってこられるお遍路さんの通り道でした。
そのお遍路さんたちのために窯元や商家の人たちが規格外れのものや半端物などを売っていたのでした。
今の陶器市の原型ともいえるでしょう。
1896年に香蘭社社長である九代深沢栄左衛門と有田陶器合資会社の社長である田代呈一らの呼びかけで日清戦争後の不況対策のために有田町桂雲寺で「陶磁器品評会」が行われました。
そして、1915年にはその品評会にあわせて、地元の陶磁器店が在庫品や規格外のものなどの大売出しをおこなったのが有田陶器市の始まりです。
期間中は町一帯に店が並び、多くの製品が並び独特の活気に満ち溢れます。
まとめ
有田陶器市は100円を切る商品から何百万円もするものまで買うことができる日本で最大の陶器市です。
直接窯元で話をしながら購入することもできますし、お店の人と値切り交渉することもできます。
人気の香蘭社や深川製磁も期間中はかなりの大盤振る舞いをするので事前にそれぞれのサイトで確認して行くのがよいでしょう。
今年のゴールデンウィークは有田陶器市で好みの品を求め、掘り出し物探しの楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょう。
ちなみに秋にも陶磁器祭りが開かれており、こちらは今年で13回目を迎えます。
春の陶器市は期間中100万人を越える人でにぎわい、毎年かなり混雑しますが、秋の陶磁器祭りはそこまで混まないので紅葉を楽しみながらゆっくり器選びをすることもできるでしょう。