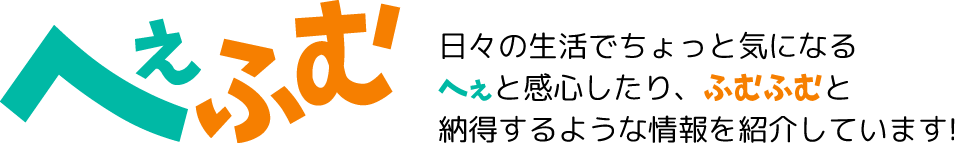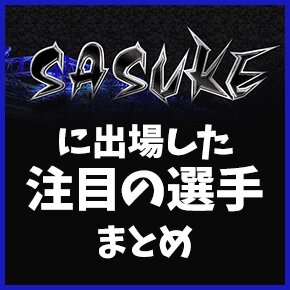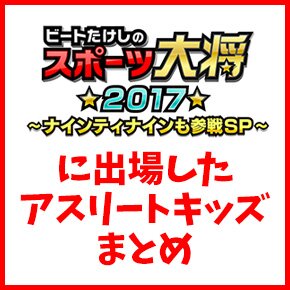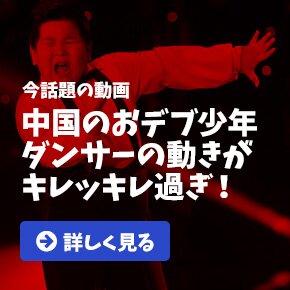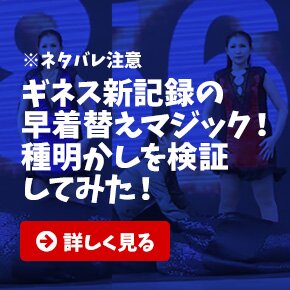多度祭りは毎年5月になると三重県桑名市の多度大社で行われる勇壮な上げ馬神事。毎年多数の来場者がつめかけて祭りを盛り上げますが、駐車場や交通規制が気になります。そこで今回は、多度祭りの開催日程やアクセスとおすすめ駐車場と交通規制情報などについてまとめてみました。
多度祭の開催日程
多度祭というのは三重県桑名市にある多度大社で毎年5月4日・5日に行われる多度大社御例祭のことですが、今年の多度祭は、5月4日(木)と5日(金)に開催されます。
多度祭のアクセス
多度祭が行われる多度大社へのアクセスです。
電車の場合
桑名駅から養老鉄道養老線に乗り換え14分ほど乗車し多度駅で下車します。
多度駅から多度大社までは歩いて20分ほどです。
多度駅から多度大社前までバスを利用すると5分ほどでバス停からは歩いて1分です。
車の場合
車の場合は東名阪の桑名東インターから10分、東名阪弥富インターから10分、名神大垣インターから20分、湾岸桑名インターから10分となります。
ただし、車利用の場合、多度祭の期間中は多度大社の無料駐車場、有料駐車場は利用できないのでご注意ください。
多度祭のおすすめ駐車場は?
多度祭を見に行く時に便利おすすめの駐車場を調べてみました。
できれば多度祭の会場になるべく近いところにとめたいと思いますよね。
多度祭の会場に近い駐車場でおすすめなのが多度町役場駐車場です。
多度祭の期間中は多度町役場のほかにも
- 多度中小学校
- 多度中学校
- 多度北小学校
- 青葉小学校
などが駐車場として開放されます。
ただし、交通規制がしかれるので駐車場までのアクセスには十分ご注意ください。
多度大社にも日ごろの参拝時には使える駐車場がありますが、多度祭期間中は使えなくなるので注意しましょう。
また国道258号線、県道、多度大社、多度駅周辺の町道は駐車禁止区間となります。
多度祭の交通規制
多度祭の期間中、JAくわな多度支店より西側及び神社周辺道路は午前9時以降、多度橋付近から須賀馬場にかけては16時ころから行事終了までの間は通行することができません。
規制区域内の住んでいる人も住民通行証がないと通行できない区域と住民通行証があっても一切通行できない区域があります。
規制区域内に親類や知人がいても通行できないようなので注意してくださいね。
多度祭の上げ馬神事
天下の奇祭といわれている多度祭の上げ馬神事の歴史は古く、南北朝時代から行われており今では三重県の無形民俗文化財に指定されています。
町内6地区から「御籤おろし」という神占いで選ばれた青年が1ヶ月近く乗馬の稽古をして騎手となり約100mほど先にあるほぼ垂直な2mほどの急な斜面を越えるもの。
選ばれた青年は朝早くと夕方に毎日乗馬の稽古をしますが、乗馬の稽古をするだけではありません。
1ヶ月ほどは「別火」といって家族と炊事の火を別々にし、魚や野菜、米を中止とした食材を用いて本人か男手が作ったものしか食べないという厳しい精進潔斎を行います。
5月2日からは「斎宿」といって神社本殿近くの川でみそぎをし、神社でお祓いを受けた布団などを各地域の集会所に持ち込んでしめ縄がはられた部屋の一角で寝泊まりをして当日を迎えるのです。

出典:https://blogs.yahoo.co.jp
乗り手はこのように日々身を清め、また乗り手だけでなく地区の青年会の人たちや地区の人たちが騎乗の稽古などにも付き合い地区をあげて支えていって行われる神事なのです。
神様に奉納する神事ですが、その絶壁を馬が越えられるかどうか、その数などによって古くから農作の時期や豊凶を占ってきました。
多くの馬が上がることができればその年は豊作、少なければ凶作。
また、最初の方の馬が上がれば早稲、中ごろの馬が上がれば中手、最後のほうの馬が上がれば晩稲の苗を選ぶというようにその年に植える稲の品種も占われてきています。
最近では景気の好況、不況も占われているようです。
騎手の衣装は4日と5日とでは変わります。
4日は陣笠裃姿で騎手ひとり2回、5日は花笠武者姿で1回ずつ激しく体を揺らす馬に乗って壁越えに挑戦します。
勇壮な上げ馬神事の一部始終をよく見るには知人友人などを募って有料の桟敷席を確保するのもよいでしょう。
多度祭の歴史
多度祭は多度大社の御例祭のことですが、歴史は古く南北朝時代の暦応年間に始まったとされています。
1571年の織田信長による長島一向一揆平定の際に神社のほとんどが焼失したため祭事も一時中断されていました。
その後多度大社は江戸時代に桑名城主本田忠勝により再興され、それからは歴代の桑名藩主により神事も連綿と継承されてきました。
現在行われている神事は1794年に記されている内容とほぼ同じ内容となっています。
祭りを見に行く側にとってはその日限りのイベントですが、その日に至るまでの乗り手や地区の人たちの日々に思いを馳せるとまた違った楽しみ方ができるでしょう。